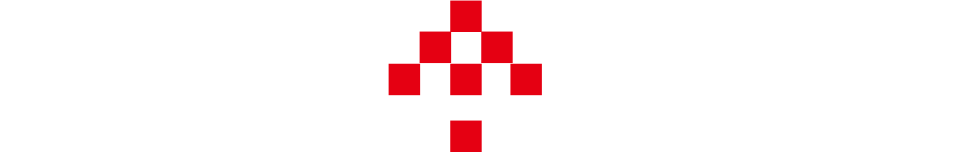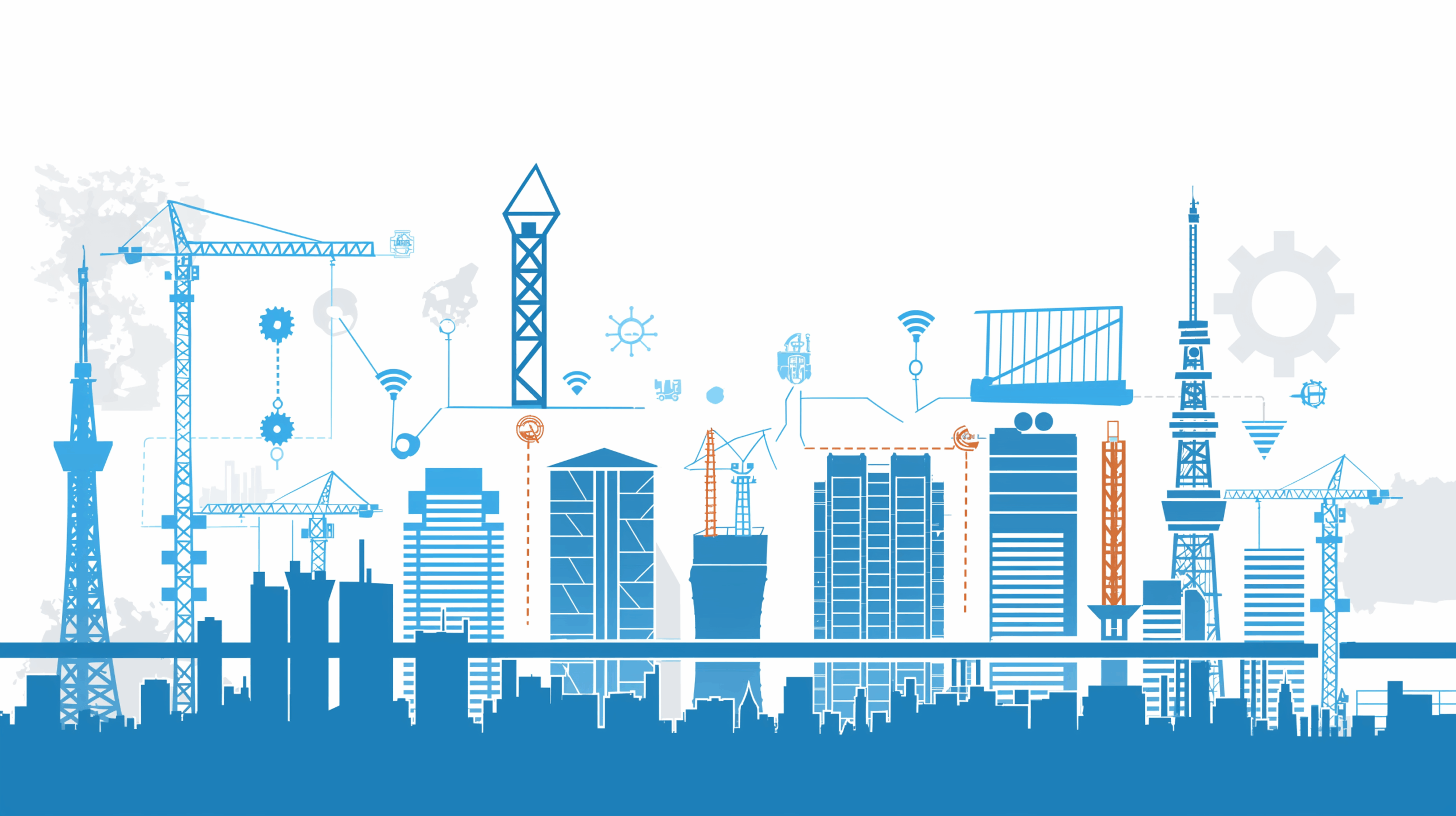
香川県高松市にある「船の体育館」として知られる旧香川県立体育館の解体工事について、県は建設会社「合田工務店」(高松市)が8億4700万円で落札したと発表しました。
「解体するだけで約8億5千万円」という金額には、県民からも驚きの声が上がっています。
老朽化と再生の是非が議論され続けた施設が、ついに新たな局面を迎えました。
「船の体育館」解体工事の概要
旧香川県立体育館は、建築家・丹下健三氏が設計した名建築として知られ、その独特なフォルムから「船の体育館」と呼ばれてきました。
老朽化により2014年に閉館して以降、保存・再生を求める建築家や市民の声も多く、県は利活用の可能性を探ってきましたが、最終的に「安全性の確保が困難」と判断し、解体を決定しました。
入札は9月上旬に実施され、「合田工務店」と「小竹組」(いずれも高松市)が応札。
予定価格約9億2千万円の一般競争入札で、技術提案や価格などを総合的に評価した結果、合田工務店が落札しました。
落札額は8億4700万円で、「建てるのではなく壊すだけでもこれだけの費用がかかる」という事実が、公共事業のスケール感を改めて示しています。
「総合評価方式」での選定
今回の入札は「総合評価落札方式」で行われ、単に安い価格を提示した業者が落札するのではなく、技術提案や施工能力も評価対象となりました。
一般競争入札では、金額勝負でコスト削減が期待できる一方で、「安かろう悪かろう」となるリスクもあります。
一方、総合評価方式は品質・安全性を重視できる反面、企画書の提出や審査が必要なため、参加のハードルが高くなります。
保存・再生を求める声も続く
「旧香川県立体育館再生委員会」(長田慶太委員長)は、県に対して公金による解体工事費の支出を取りやめるよう求める住民監査請求を提出しています。
文化的価値を守りたい建築家や市民と、安全面や維持費を重視する行政との間で意見が割れる構図です。
県は今月中に仮契約を結び、議会承認を経て本契約へと進む見通しですが、「象徴的な建築の行く末」と「公共事業の判断基準」が問われる事例となっています。
運営者所感
今回の事例は、「公共建築の価値をどう扱うか」という難しいテーマを改めて浮き彫りにしました。
老朽化した施設の再生には莫大な費用と時間がかかる一方、解体にも数億円単位のコストが発生します。
「解体に8億円超」という数字は、自治体の財政規模を考えると非常に大きなインパクトです。
入札面では、価格だけでなく品質や技術提案を評価する総合評価方式が採用され、妥当な判断だったと言えるでしょう。
安価な入札に偏ればコスト削減はできますが、施工不良や安全面でのトラブルが後を絶ちません。
一方、総合評価方式は企業側の負担が増えるものの、公共インフラの品質確保には欠かせない仕組みです。
重要なのは、「入札方式そのもの」よりも、事業の目的に応じて適切な方式を選ぶこと。
歴史的価値のある施設や大規模工事では、価格競争だけに頼らない判断が求められます。
最後に
公共調達や入札の制度は、案件ごとに条件や背景が異なり、表面的な結果だけを見ていても全体像は見えにくいものです。
当サイトでは、入札結果やニュースを単発で追うのではなく、制度・条件・背景を含めて整理し、比較できる情報をまとめています。
「自分に関係のある入札や制度を効率よく把握したい」
「条件の違いを整理して判断したい」
そんな方は、入札情報を比較・整理したページも参考にしてみてください。