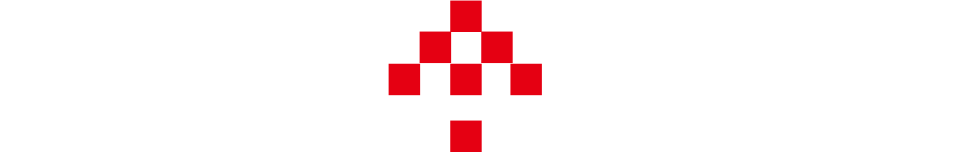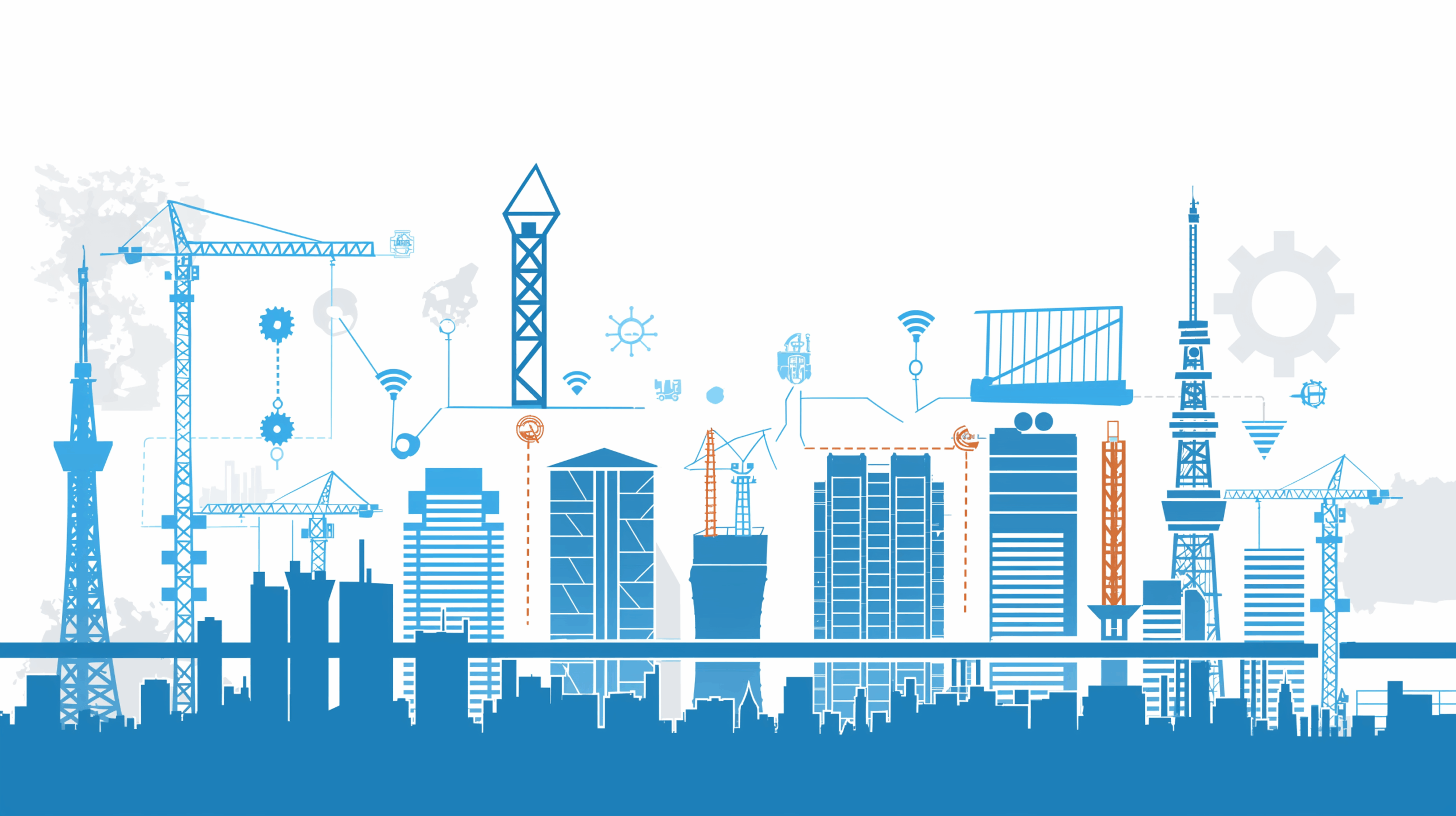
さいたま市は2025年10月29日、さいたま新都心への新庁舎移転計画の基本設計(素案)を公表しました。新庁舎は、合併30年の節目となる2031年度を目途に、さいたま新都心への移転・供用開始を目指しています。
2021年12月時点では、約238億円とされていた概算事業費でしたが、今回の発表では約3倍の約700億円に増加。市内では100億円台の公共事業でも入札不調が相次いでおり、700億円規模の大型案件がどのような条件で発注されるか、また実際に応札者が集まるかが懸念されます。
さいたま新都心の新庁舎整備の概要
地下1階・地上18階の行政棟、地下1階・地上4階の議会棟、地上3階の中広場棟の3棟で構成される新庁舎は、敷地面積が約1万5,000平方メートル、延べ床面積は約6万4,000平方メートルに及び、JRさいたま新都心駅からの歩行者デッキの延伸整備や、外構整備も一体で行われる計画です。
新庁舎は、行政・議会機能を集約し、防災拠点としての機能も備えています。また、市民が立ち寄れるシンボル的な空間も意識されており、「開かれた市政の拠点」としての役割が期待されています。
さいたま新都心は交通の利便性が高く、国や県の機関も集積していることから、市は「市民サービスの向上」と「他機関との連携強化」を移転の主な理由として挙げています。これは政令指定都市として、今後も質の高い行政サービスを安定的に提供するための拠点づくりという位置づけです。
設計は公募型プロポーザルにより、アール・アイ・エー・環境デザイン研究所設計共同体が選定されました。市は2026年4月に基本設計を確定し、その後、実施設計・施工を一括で発注する方針を示しています。
238億円から700億円へ―事業費増加の背景
2021年12月の基本構想では約238億円とされていた概算事業費は、2023年11月の審議会では約400億円に、2025年10月の基本設計(素案)では約700億円へと段階的に上昇しています。わずか4年で当初の約3倍という規模の膨張は、公共事業の計画・実行における課題を改めて浮き彫りにしました。
市は、事業費が約3倍まで増えた主な理由として、資材・人件費の高騰、設計の詳細化による面積増、防災機能や市民利用スペースなどの拡充を挙げています。特に本体工事費は、前回試算の391億円から640億円へと大幅に膨れ上がりました。市は、同じ水準でコスト上昇が続いた場合、2026年7月の事業者選定手続き時には、約750億円から約770億円に達する可能性があることも示唆しています。
なぜ浦和からさいたま新都心に移転させるのか
新庁舎の移転理由として、現庁舎の老朽化、分散している行政機能を1か所に集約する必要性、新都心には国・県の機関が集まっており連携がしやすいこと、さらに災害時の司令塔として必要な耐震性能や防災機能を現庁舎では確保しにくいこと、などが挙げられています。
一方で、2021年度のパブリック・コメントでは「現在地で建て替えればコストを抑えられるのでは」「移転後の浦和地区の整備にも費用がかかる」といった慎重な意見も寄せられています。事業費が当初の概算から約3倍にも跳ね上がってしまったこともあり、市民への丁寧な説明が引き続き求められる状況です。
さいたま市で相次ぐ入札不調
今回の新庁舎は規模が大きいだけに、さいたま市内で立て続けに起きている入札不調の状況にも目を向けておく必要があります。
さいたま市は、131億円で予定していた「(仮称)次世代型スポーツ施設整備事業」を総合評価一般競争入札で公告しましたが、資材・人件費の高騰などで市の想定と事業者側の積算が合わず、入札参加者が辞退して手続きが中止となりました。
さらに、さいたま市南区・武蔵浦和駅周辺で計画されていた3,700人規模の義務教育学校でも、1回目の入札は参加者ゼロで不調に終わりました。市は直ちに再公告を行い、予定価格を148億6,100万円から163億4,600万円へと引き上げ、工期も延長しましたが、それでも応札が集まらず2回目も不調となりました。
こうした入札不調は全国的な課題となっており、東京都江戸川区では新庁舎の供用開始を約2年延期、仙台市では空調設備工事で半年以上の遅延が発生するなど、大型公共事業で同様の事態が相次いでいます。
運営者所感
現段階ですでに約700億円、場合によっては約770億円規模の大型公共事業となりますと、実際に応札できるのは大手ゼネコンやそれらを中心としたJVに限られてくるでしょう。
市が示しているような実施設計と施工を一括で発注する方式であれば、技術力・施工体制・工期の妥当性なども含めて総合的に評価する”実質的な総合評価方式”になると考えられます。この場合、事業者側は公告が出てから準備を始めるのでは到底間に合わず、事前のJV組成や技術提案内容の検討が不可欠になります。
ただ、さいたま市内では近年、100億円超えの規模の案件でさえ入札不調が立て続けに起きています。これは単に「事業者の応札意欲が低い」という問題ではなく、「自治体の想定する予定価格」と「施工側の実勢価格」に大きな乖離が生じていることを示しています。
入札不調を防ぐためには、物価スライド条項の明確化、リスク分担の適正化、工期設定の現実性、出来高払いの導入など、発注条件の細部を市場実勢に即して設計することが重要です。特に長期にわたる大型案件では、価格変動リスクを発注者・受注者でどう分担するかが、事業者の参入判断を左右します。
また今回のような大規模案件では、主体工事は大手ゼネコンが中心となりますが、設備工事や外構工事の一部が分離発注されれば、地元の中小企業にも参入機会が生まれる可能性があります。実際、全国的にも分離・分割発注の活用が推奨されており、地域経済への波及効果を高める手法として注目されています。
新庁舎が完成すれば、政令指定都市の”顔”となる建物だけに、市場の実情を踏まえた発注条件の設計と、事業者側の技術力・提案力の両方が問われる案件です。2026年度以降の公告内容と、それに対する市場の反応を注視していく必要があるでしょう。
最後に
公共調達や入札の制度は、案件ごとに条件や背景が異なり、表面的な結果だけを見ていても全体像は見えにくいものです。
当サイトでは、入札結果やニュースを単発で追うのではなく、制度・条件・背景を含めて整理し、比較できる情報をまとめています。
「自分に関係のある入札や制度を効率よく把握したい」
「条件の違いを整理して判断したい」
そんな方は、入札情報を比較・整理したページも参考にしてみてください。
関連リンク
ニュース元:
Yahoo!ニュース|さいたま市新庁舎 総事業費は700億円に増 3棟で構成、地下1階、地上18階 さいたま新都心駅からデッキ延伸整備