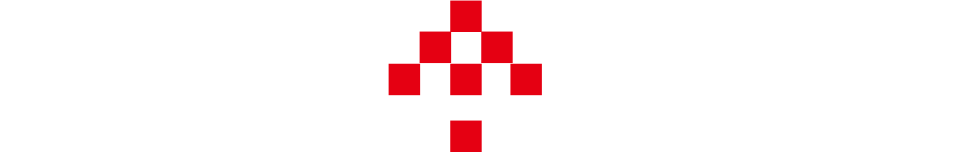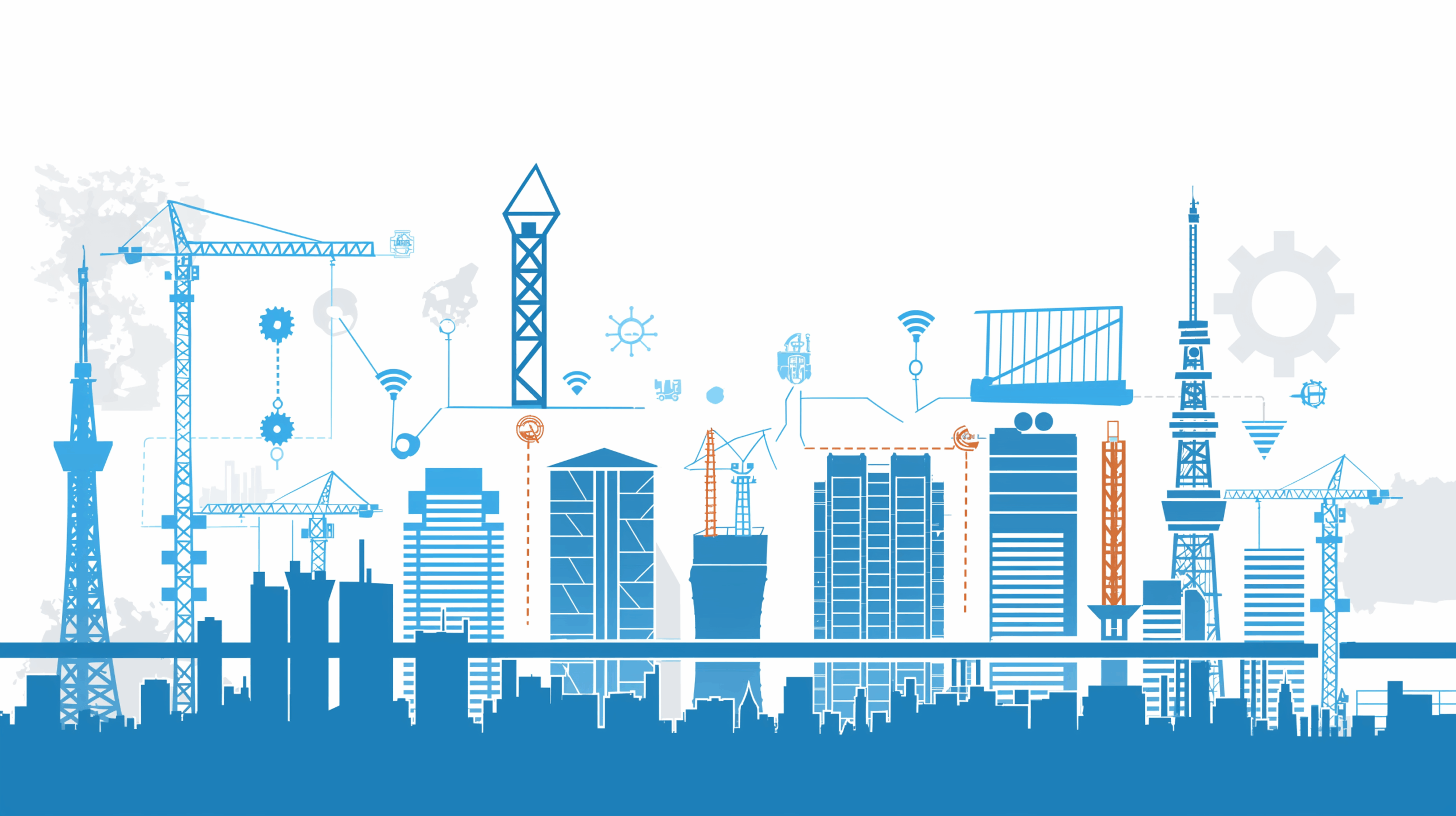
大分県は11月4日、クラサスドーム大分の可動屋根の修理に約30億円を投じる方針を発表しました。2024年6月から老朽化のため開閉を停止していた屋根について、県は3か年計画で修繕を進める考えを示しています。
2001年の完成から24年が経過したドームの屋根は、2024年6月までの1年間で40往復の稼働実績があるものの、可動屋根の修復に約30億円もかかることに対して、県民や専門家からは費用対効果を疑問視する声が上がっています。
今回の事例は、大型公共施設の維持管理と、限られた予算の中での優先順位づけが問われるケースです。
クラサスドーム大分の屋根修理計画の概要
クラサスドーム大分は、大分トリニータの試合をはじめ、ラグビー・陸上競技などのスポーツやイベントに使われている多目的施設です。収容人数は40,000人、107×71mのフィールドと400m×9レーンのトラックを備えた大規模な施設となっています。
ドームの大きな特徴である開閉式の屋根は、白い屋根部分が中央に向かって動く仕組みになっていますが、2024年6月から開閉を停止していました。
屋根の開閉停止は、目視点検で問題が確認されたことを受けた措置です。県のその後の調査(2024年9~10月)では、20本のワイヤーロープのうち、メインスタンド側で4本、バックスタンド側で1本に交換が必要な断線が見つかり、交換基準に達した計5本を含む10本を取り替える方針が示されています。
佐藤知事は「おおむね3年をかけて(ワイヤーの)取替を行い、費用はおおよそ30億円を見込んでいる」と述べ、機能回復を優先する考えを示しています。
30億円の内訳―なぜこれほどの費用がかかるのか
約30億円という修理費用の内訳は、直径75mmの鋼製ワイヤーロープ10本と直径66cmの滑車160個の材料費として約15億円、作業員の人件費などで約10億円、仮設足場の設置などの安全対策費が5億円から6億円とされています。
なぜ、これほどの費用がかかるのでしょうか。その理由は、施設の特殊性にあります。
まず、クラサスドーム大分は、建物の外周が約800m、可動屋根の直径は約274mにも及ぶ規模の施設です。ドームの最高高さは約57.46mで、これは約20階建てビルに相当します。これほどの高所での作業となると、足場の組み立てと撤去だけでも相当な時間と費用がかかります。安全面の確保も厳重に行う必要があります。
さらにドーム屋根が曲面であるため、曲線用部材や吊り足場など”曲面対応の仮設計画”が必要となり、平面屋根より足場計画が複雑化してしまうのです。
これらの条件が重なったことで、約30億円規模になったという見立てです。
なぜ修理が必要なのか
県が修理を決断した背景には、複数の要因があります。
まず、大分陸上競技協会など10団体から「屋根が無いと猛暑や雨によって競技記録に影響が出ることがある。障がい者スポーツでは少しの雨で中止になることもある」という理由で、可動屋根の再開を求める要望書が県に提出されたことが挙げられます。
また、広域防災拠点としての機能も重要視されています。災害時には物資の保管や仕分け作業場として使用されるため、開閉式の機能が必要とされています。天候に左右されずに大量の物資を管理できることは、防災拠点として不可欠な要素です。
さらに、今年8月には人気アーティストのライブが開かれるなど、大型イベント開催時にも開閉式屋根が必要であることが示されました。佐藤知事は、「今年の夏にあった大規模なコンサートの開催で、イベント利用のポテンシャルを感じた」と述べており、スポーツ以外の用途での活用可能性も視野に入れています。
費用対効果への疑問
稼働実績は、屋根の開閉を停止する2024年6月までの1年間では、年間40往復でした。これは平均すると9日に1回のペース。イベントやサッカーの開催時に動くことが多く、1回動かす費用は2万8,100円とされています。
この数字だけを見ると、年間40往復の稼働のために約30億円を投じることへの疑問が浮かびます。大分市民からも「閉まってもらった方がいいが、ちょっと高いな」「なんで30億もなの。最初作った時点で計算で分かってるでしょ」といった声が報じられています。
また、地方行政に詳しい日本文理大学の長崎浩介教授は、「インフラ投資が場当たり的な印象を受けた。コストと便益を比較できる情報や、長期的な修繕計画が不足している。道路・学校など他のインフラとのバランスが適切かどうかが分からない。県民への説明が足りないのでは」と指摘。費用対効果の説明責任が論点になっているという構図です。
可動屋根の修理は、他の公共インフラ整備と比較してどの程度の優先度なのか、また今後の維持管理費用はどの程度見込まれるのか。こうした点について、県民が納得できる説明が求められています。
運営者所感
今回の事態には、自治体側の維持管理体制の問題が浮き彫りになっています。ワイヤーの耐用年数は約15年とされていたにもかかわらず、2001年のドーム完成から24年間一度も交換されていませんでした。計画的に更新していれば、作業規模も小さく費用も分散できたはずです。
県は、早ければ2026年度から3か年計画で改修を実施するとしています。ただ、入札に関する詳細な条件はまだ示されていません。この規模の特殊工事となると、高所・特殊仮設・工程制約への対応実績が求められるため、要件次第では共同企業体(JV)等も想定されます。曲面上での作業という技術的な難しさを考えると、施工管理能力の高い事業者でなければ対応は難しい、という見方です。
全国的に入札不調が続く中、物価スライド条項の明確化、リスク分担の適正化、工期設定の現実性といった発注条件を市場実勢に即して設計することが重要とみられます。県は今後、費用対効果の詳細な分析と入札条件の詳細を示すことで、県民の理解を得ていく必要があるでしょう。
最後に
公共調達や入札の制度は、案件ごとに条件や背景が異なり、表面的な結果だけを見ていても全体像は見えにくいものです。
当サイトでは、入札結果やニュースを単発で追うのではなく、制度・条件・背景を含めて整理し、比較できる情報をまとめています。
「自分に関係のある入札や制度を効率よく把握したい」
「条件の違いを整理して判断したい」
そんな方は、入札情報を比較・整理したページも参考にしてみてください。