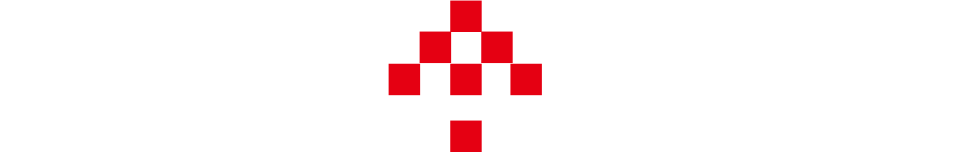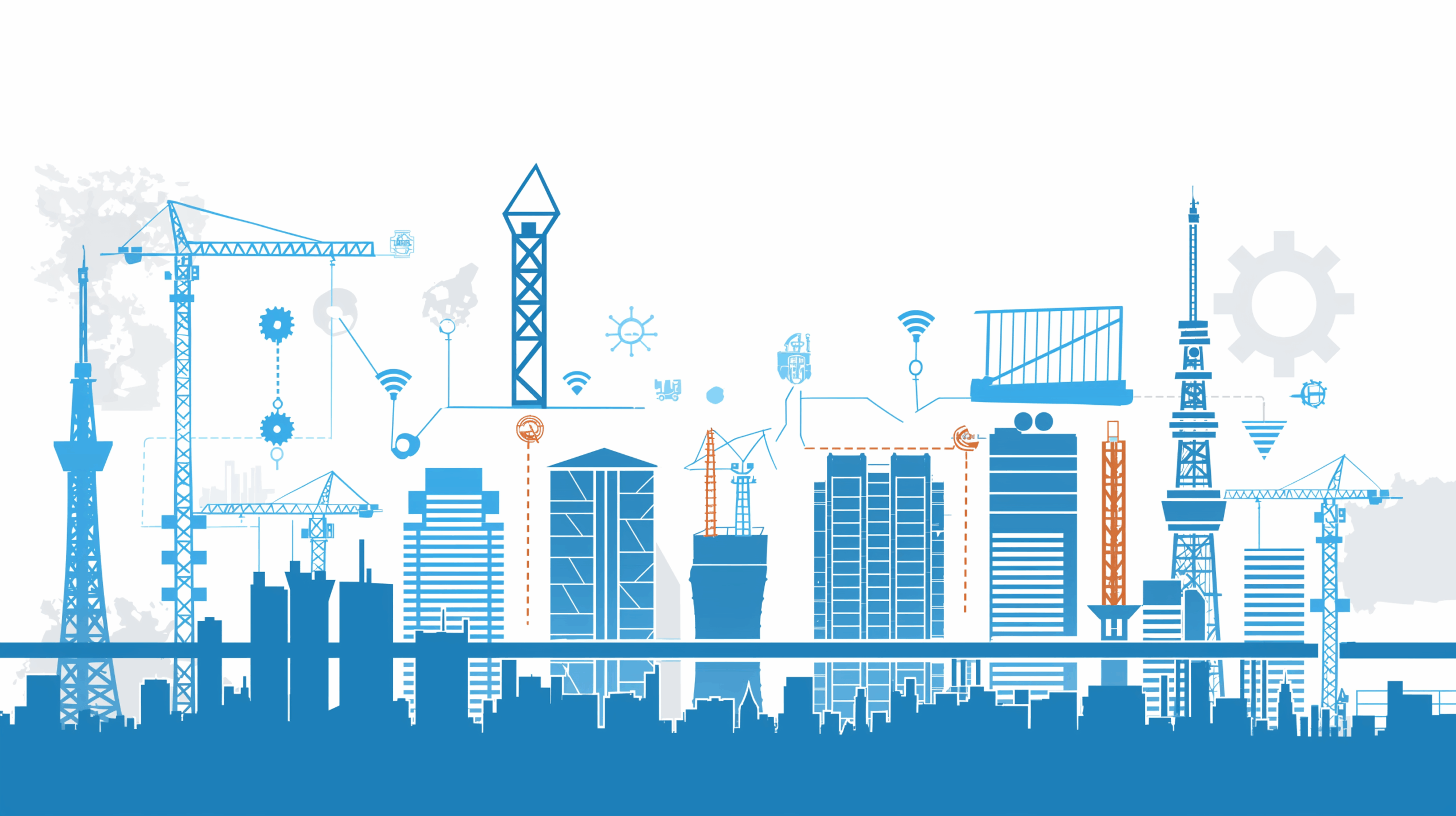
東京都江戸川区で、一般競争入札を避けるために工事契約を分割して発注していた問題で、弁護士らによる第三者委員会が10月17日に調査報告書を公表しました。
報告書では、不適切な契約が過去5年間で1642件に上るとされ、区の組織文化として「分割入札が正々堂々と受け継がれていた」と厳しく指摘しています。
第三者委員会が指摘する「構造的な問題」
調査によると、江戸川区では、一般競争入札が必要な金額を避けるために「130万円未満」に分割して発注する手法が長年行われていました。
この手法は一部職員だけの問題ではなく、20年以上にわたり組織的に引き継がれてきたとされています。
委員長の野村裕弁護士は、「契約に対する意識が欠如しており、法令遵守よりも慣習が優先されていた」と述べ、行政組織全体に根深い問題があることを示唆しました。
区の対応と再発防止策
江戸川区の斉藤猛区長は、「提言を基に対応策を速やかに作成し、区民の信頼回復に努めたい」とコメント。
今後は、契約審査の仕組みを強化するとともに、職員教育や監視体制の見直しが進められる見通しです。
ただし、今回の件は「制度上のチェック体制があったにもかかわらず、内部で形骸化していた」点が大きな課題といえます。仕組みを整えるだけでなく、現場でどう運用されるかが再発防止の鍵になるでしょう。
制度面から見る「分割入札」の問題点
本来、入札制度は透明性と公正性の確保を目的としています。
しかし、今回のように契約金額を分割して入札を回避すると、
- 競争原理が働かず、価格や品質の適正評価が失われる
- 特定業者に仕事が集中し、癒着や不正の温床になる
といったリスクが生じます。
特に「分割発注」は一見小さな工夫のようでも、公平な入札制度の信頼性を根底から揺るがす行為といえます。
運営者所感
このニュースは、「入札制度の仕組みを守ることの難しさ」を象徴しています。
制度そのものは透明性を保つために設計されていても、現場レベルで“慣習化した抜け道”が存在すると、公正な競争が成立しなくなります。
一方で、現場の職員から見れば「年度内に工事を終わらせたい」「業者を待たせたくない」といった“実務的な事情”もあるのかもしれません。
しかし、公金を扱う入札においては、「スピードよりも透明性」を優先すべきです。
今後は、形式的なマニュアルではなく、現場が自ら「公正な契約とは何か」を考えられるような仕組みづくりが必要だと感じます。
最後に
公共調達や入札の制度は、案件ごとに条件や背景が異なり、表面的な結果だけを見ていても全体像は見えにくいものです。
当サイトでは、入札結果やニュースを単発で追うのではなく、制度・条件・背景を含めて整理し、比較できる情報をまとめています。
「自分に関係のある入札や制度を効率よく把握したい」
「条件の違いを整理して判断したい」
そんな方は、入札情報を比較・整理したページも参考にしてみてください。