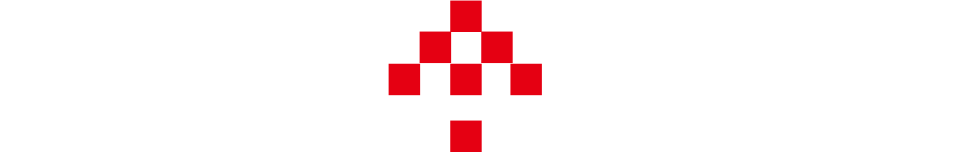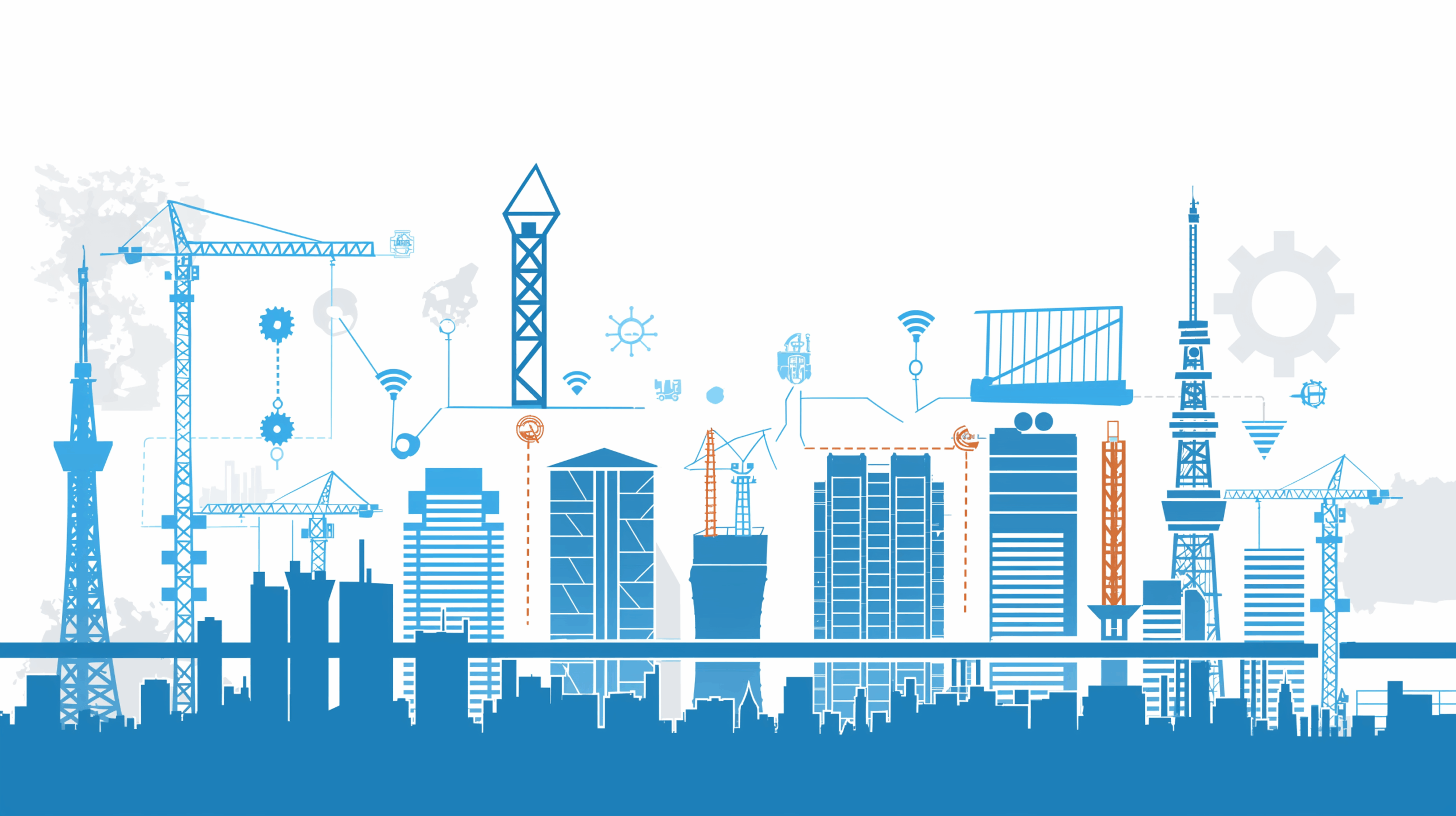
公共調達の現場で“入札不調”が続いた結果、国立劇場(東京都千代田区)の建て替えスケジュールが見直され、再開時期の目標が「33年度」へと後ろ倒しになりました。文化庁は、2025年度に入札公告、2027年度に契約締結という新たな工程を示し、老朽化により2023年に閉場した劇場の再開に向けて仕切り直しを図ります。1966年開場以来、歌舞伎や文楽など伝統芸能の拠点としての役割を担ってきた施設だけに、今回の発表は関係者に大きな影響を与えそうです。
今回のニュースの要点
文化庁は建て替えを巡る整備計画を見直し、再開目標を33年度に設定しました。当初は29年度末の再開を見込んでいたものの、入札に応募者が現れない、あるいは予定価格を大幅に上回る――といった典型的な“入札不調”が続き、工程の再構築が不可避になった格好です。新しいロードマップでは、25年度に入札公告、27年度に契約締結という節目を置き、そこから本格的な施工に入る見立てです。
影響と注目点
国立劇場は単なるホールではなく、公演と担い手育成の両輪で日本の伝統芸能を支えてきました。再開時期の後ずれは、出演団体や関連産業、教育・研修の現場にも長期の計画修正を迫ります。一方で、計画の出直しは仕様や工期、コストの前提を現実的に再設定する機会にもなります。資材・人件費の高止まり、技能者不足、長工期案件に伴うリスク配分など、全国の大規模公共案件が直面する課題に照らし、入札条件の設計次第で不調の再発は抑制しうるからです。
今後の見通し
直近のマイルストーンは25年度の入札公告です。ここで示される発注方式(総合評価の配点、工期の設定、価格変動条項や出来高払いなどのリスク分担)が、応募姿勢と競争度合いを左右します。27年度の契約締結までに、工法・工程の合理化や分離・分割発注の活用、JV(共同企業体)前提の規模設計など、参加障壁を下げる工夫がどこまで盛り込まれるかも注視点です。いずれにせよ、33年度再開というターゲットに向け、無理のない工程管理と市場実勢に寄り添った条件設計が鍵になります。
運営者所感
“入札不調”は、受注者側の意欲不足というより、価格・工期・リスク配分が市場実勢と乖離したときに起きやすい現象です。昨今の建設市場は、資材費・人件費の上昇、技能者の逼迫、長期案件特有の不確実性が重なり、「背伸びすれば赤字になりかねない」環境です。したがって、物価スライド条項やリスク共有の明確化、工期に余裕を持たせた設計、分離発注の活用など、発注者側の工夫が応募意欲を引き上げます。受注者側も、早期のJV組成や代替工法の提案準備、コスト構造の可視化を進めることで、総合評価での訴求力を高められるはずです。国立劇場の再整備は文化資産の継承に直結する大事業。“発注条件の現実解”と“施工能力の総動員”――この二つがかみ合えば、再開までの道筋は見えてくると考えます。