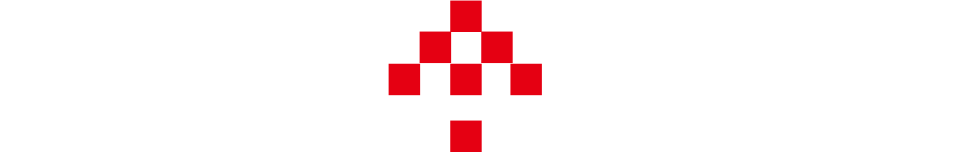愛知県内で公共工事や物品・役務の調達といった入札に参加するためには、各自治体が定める「入札参加資格」を事前に取得する必要があります。
ただし、愛知県では大きく分けて次の二つの仕組みが存在しています。
- 愛知県庁と共通システムを利用する市町村
- 名古屋市の入札参加資格制度
この記事では、それぞれの特徴と違い、さらに共通システムを利用している自治体の一覧を整理しました。ました。
愛知県庁と共通システムを利用する市町村の入札参加資格
愛知県庁をはじめ、県内の多くの市町村では便利な「あいち電子調達共同システム」を利用しています。
このシステムに登録しておけば、対象となる複数の自治体で幅広く入札に参加できるのが大きなメリットです。
あいち電子調達共同システムとは
- 愛知県の電子調達共同システムは共通の枠組みの中で、次の二つの入口に分かれています。
- 物品・役務関係 :「電子調達共同システム(物品等)」
- 工事・コンサル関係:「電子調達共同システム(CALS/EC)」
- いずれも電子申請と書類提出を組み合わせて資格審査を行い、名簿に登載される仕組みです。
特徴
- 物品・役務、建設工事、設計測量などの区分ごとに資格を取得する必要がある
- 一度の申請で複数自治体に対応可能
- 定時受付と随時受付があり、有効期間は約2年間です。現在受付中なのは、令和6・7年度入札参加資格(2024年〜2026年度有効)です。
利用自治体一覧
| 区分 | 自治体 |
|---|---|
| 県庁 | 愛知県 |
| 区分 | 自治体 |
|---|---|
| 市 | 豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市 |
| 区分 | 自治体 |
|---|---|
| 町村 | 東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村 |
| 区分 | 自治体・団体 |
|---|---|
| 組合・団体 | 名古屋港管理組合、海部南部水道企業団、小牧岩倉衛生組合、尾三消防組合、愛知中部水道企業団、五条広域事務組合、愛知県住宅供給公社、公益財団法人愛知水と緑の公社、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会、西春日井広域事務組合 |
※2025年8月時点での公式公開情報に基づく一覧表
名古屋市の入札参加資格制度|申請方法と有効期間のポイント
名古屋市は「あいち電子調達共同システム」を利用していません。
そのため、名古屋市での入札参加を希望する場合は、愛知県庁や他の市町村とは別に独自の申請手続きが必要です。
特徴
- 名古屋市独自の入札参加資格制度(あいち電子調達共同システムの資格は利用できない)
- 2年ごとに更新が必要
- 電子申請+書類提出の2段階方式
- 入札参加には原則としてICカードの取得と登録が必要(ただし、少額随意契約のみ参加の場合はICカード不要で、ID・パスワード方式で参加可能)
つまり、愛知県庁や共通システムで資格を取っていても、名古屋市に参加したい場合は別途申請が必要になります。
申請の流れ
- 入札参加者登録システムで業種を選択・入力
- データ送信後、印刷した申請書と必要書類を郵送または持参
- 書類が到着した時点で受付完了
- 審査終了後、有資格者名簿に登載され、通知書が発行
共通システムと名古屋市の違いの整理
- 愛知県庁と共通システムを利用する市町村 → 一度の申請で複数自治体に対応できる
- 名古屋市 → 独自制度を採用しており、別途申請が必要
- 共通システムは「物品等」「CALS/EC」に分かれ、対象区分は自治体ごとに異なる
- 名古屋市はICカード必須、等級区分の基準金額も市独自に設定
まとめ|愛知県と名古屋市の入札参加資格は両方の登録がおすすめ
- 愛知県内で入札に参加するなら、まずは「愛知県庁と共通システムを利用する市町村」への登録が基本
- 名古屋市の案件にも参加したい場合は、別途「名古屋市」の資格申請が必要
- 小規模町村では対象区分が限られているため、自社の業種に応じて事前確認が必須
広域で営業している企業や、名古屋市との取引を希望する企業は、両方の資格を取得しておくのが安心です。
様々な入札情報を入手するためにサービスを利用する
愛知県内に限らず、様々な都道府県、市町村のビジネスチャンスにつながる入札案件を探していく場合は、自社で全てを収集することは難しい作業になります。
広く情報を収集する場合は、入札情報サービスを利用して収集することをおすすめします。入札情報サービスはいくつか存在しますが、その多くが無料でお試しができるようになっています。気になるものがあればお試しで利用をして、自社にとって利便性の高いサービスを選びましょう。
当サイトでは様々な入札情報サービスをランキング形式で紹介しています。料金や収集対象の違いなどをより詳しく紹介していますので、興味のある方はおすすめの入札情報サービスをランキング形式で紹介!もご覧ください。